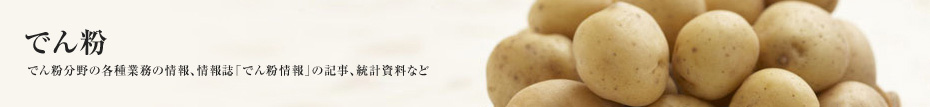
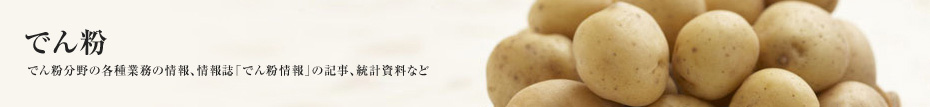
ホーム > でん粉 > 各種業務の実施に関する情報 > よくあるご質問(でん粉関係業務) > よくあるご質問(交付金の対象生産者要件について)
最終更新日:2025年8月22日
Q1 どのような生産者が交付金の交付対象者になりますか。
A1
交付対象者は、安定的な生産体制の確立を図る観点から、
(1)認定農業者等(B−1)
(2)一定の収穫面積を有する者(B−2)
(3)一定の収穫面積を有する協業組織(B−2)
(4)一定の基幹作業面積を有する共同利用組織に参加している者(B−3)
(5)(1)、(2)若しくは(3)の要件を満たす者又は一定の基幹作業面積を有する受託組織等
に基幹作業を委託している者(B−4)
のいずれかに該当する生産者となります。
また、上記に加え、所属するかんしょのでん粉製造事業者とあらかじめ売渡しに関する契約を締結していること及び生産者自身が環境規範を遵守することが要件とされています。
※ 「基幹作業」とは、かんしょの栽培に関する育苗、耕起及び整地、畝立て、植付け、防除
又は収穫のことをいいます。
(1)認定農業者等(B−1)
(2)一定の収穫面積を有する者(B−2)
(3)一定の収穫面積を有する協業組織(B−2)
(4)一定の基幹作業面積を有する共同利用組織に参加している者(B−3)
(5)(1)、(2)若しくは(3)の要件を満たす者又は一定の基幹作業面積を有する受託組織等
に基幹作業を委託している者(B−4)
のいずれかに該当する生産者となります。
また、上記に加え、所属するかんしょのでん粉製造事業者とあらかじめ売渡しに関する契約を締結していること及び生産者自身が環境規範を遵守することが要件とされています。
※ 「基幹作業」とは、かんしょの栽培に関する育苗、耕起及び整地、畝立て、植付け、防除
又は収穫のことをいいます。
Q2 でん粉原料用かんしょを生産する地域はどこでもいいのですか。
A2
交付金の対象となるでん粉原料用かんしょの生産地域は、農林水産省の告示で定められており、現在は宮崎県及び鹿児島県となります。
Q3 B−1の認定農業者等の要件は、どのようなものですか。
A3
でん粉原料用かんしょを生産している認定農業者等であれば、収穫面積にかかわらず、交付金の交付対象者になれます。
認定農業者制度の詳細については、下記 農林水産省のホームページをご覧ください。
〇農林水産省「認定農業者制度について」
https://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/seido_ninaite.html
認定農業者制度の詳細については、下記 農林水産省のホームページをご覧ください。
〇農林水産省「認定農業者制度について」
https://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/seido_ninaite.html
Q4 B−2の一定の収穫面積を有する者の要件は、どのようなものですか。
A4
自ら収穫作業を行う面積が、0.5ha以上のでん粉原料用かんしょ生産者であることです。収穫面積の計算方法は、「自らの作付地(当年産として収穫する部分に限る。)」+「他の者から収穫作業を受託した面積」−「他の者に収穫作業を委託した面積」となります。
Q5 B−2の協業組織の要件は、どのようなものですか。
A5
効率的な生産が図られるものとする観点から、3.5ha以上の収穫面積を有することに加え、
(1)組織の規約を作成していること
(2)事業計画及び収支予算が作成され、計画に従って組織として営農活動(でん粉原料用か
んしょの生産・販売)が行われていること
(3)基幹作業に係る管理者(オペレーター)が定められていること
(4)農業共済に加入する場合は、構成員個人で加入するのではなく組織名義で加入すること
が必要となります。
(1)組織の規約を作成していること
(2)事業計画及び収支予算が作成され、計画に従って組織として営農活動(でん粉原料用か
んしょの生産・販売)が行われていること
(3)基幹作業に係る管理者(オペレーター)が定められていること
(4)農業共済に加入する場合は、構成員個人で加入するのではなく組織名義で加入すること
が必要となります。
Q6 B−3の共同利用組織の要件は、どのようなものですか。
A6
効率的な生産が図られるものとする観点から、機械の共同利用又は共同出役により3.5ha以上基幹作業を共同して行うことに加え、
(1)組織の規約を作成していること
(2)基幹作業に係る管理者(オペレーター)が定められていること
が必要となります。
(1)組織の規約を作成していること
(2)基幹作業に係る管理者(オペレーター)が定められていること
が必要となります。
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 特産運営部 (担当:特産原料課)
Tel:03-3583-8960
農畜産業振興機構 特産運営部 (担当:特産原料課)
Tel:03-3583-8960










